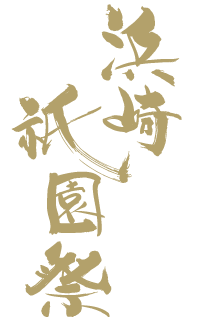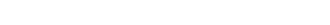 |
|
● 一日目 |
|
10:00 |
|
祈願祭神事
祇園社に山笠関係者が集まり、神主によりおごそかに神事が執り行われます。
当番区による山囃子が数曲奉納され、浜・東・西区がそれぞれに御幣をもらい、天上屋形の上に取り付けて午後3時の曳き出しに備えます。
神様が宿るとされている「天上屋形」に御幣を付けた後は、祭りが終わるまでは触ってはいけない、と伝えられています。
|
 |
|
|
|
15:00 |
|
曳き出し
西区山笠 諏訪神社出発
開会式が執り行われるひきやま公園に向かって出発します。
|
|
|
|
|
15:20 |
|
開会式
ひきやま公園に濱・東・西区の山笠が揃い、
開会式が行われます。
いよいよ、浜崎祇園祭の始まりです!
|
 |
 |
|
|
|
15:40 |
|
ひきやま公園出発
濱区・東区・西区の順で出発し、町内を練り歩きます。
道行の囃子の音色と車輪のきしむ音。たぎります!
浜崎四つ角・浜玉支所前信号交差点のコーナリングも見ものです! |
 |
|
|
|
16:20 |
|
居酒屋 一文銭前 おおまぎり
「おおまぎり」とは、山笠を何度も旋回させることで、第一の見せ場です。
このおおまぎりは大変危険であるため、基本的に子供の参加は認められていません。祭りの中で最も緊張する場面であり、興奮する場面でもあります。 |
 |
|
|
|
|
|
お汐井とり
おおまぎりの後180度の方向転換をおこない、山笠を据えた後、夕日の沈む浜崎海岸へ「お汐井」(浜崎海岸の海の砂)を汲みに行きます。
「お汐井」を汲むために神社から浜へ向かって巡行し、汲んで神社に帰ってくる、というのが山笠の道行きの意味になっています。
各区ごと、それぞれ代表者一人が海に入り砂を取ります。これは未婚の者の仕事とされています。また、砂は粒の粗いものが好まれます。
取ったお汐井は山笠の前方に吊るされ、巡行中に怪我をしないよう、また巡行に参加しない人もお清めに貰い、体にかけたり、舐めたりします。 |
 |
 |
|
|
|
19:00 |
|
濱区出発
燈籠に灯りが灯され、宵山の始まりです。
行きとは逆に、西区・東区・濱区の順番で、諏訪神社に向かって曳き出します。 |
 |
|
|
|
19:45 |
|
東区出発
宵の口、揺れる燈籠の灯りが美しくなるころです。 |
 |
|
|
|
20:15 |
|
井久保商店前出発 - 諏訪神社前 おおまぎり
浜崎祇園祭が最高潮を迎えます。おおまぎりの回数は決められていませんが、十数回程度、回します。
巡行時間の規制が緩かったころは、数十回 回ることもありました。
|
 |
|
|
|
22:00 |
|
おおまぎり終了 |
 |
|
● 二日目 |
|
|
|
15:00 |
|
諏訪神社 濱区・東区・西区の順で出発。1日目と同じルートで巡行します。 |
|
15:40 |
|
東区出発 |
|
16:25 |
|
鬼塚鮮魚店前 おおまぎり |
|
18:50 |
|
濱区出発 (西区・東区・濱区)の順で出発 |
|
19:40 |
|
東区出発 |
|
|
|
20:15 |
|
居酒屋 一文銭前出発 - 諏訪神社前おおまぎり
クライマックスです。名残惜しいかのように、何度も「おおまぎり」が行われ、観客の皆さんからも拍手が起こります。 |
 |
|
|
|
21:15 |
|
濱区・東区 諏訪神社前出発 各地区へ。
各地区で最後の「おおまぎり」をおこない、その後山笠を据えて数曲山囃子を囃し、山笠を納めます。
そして祇園社へ無事故で山笠奉納行事が終わったことのお礼参りを行います。
|
 |
|
|
|
26:00 |
|
山解き開始。
日が昇りかける午前6時前には、台車から全て山小屋に納められます。
境内のアスファルト路面に刻みついたおおまぎりの車輪の跡だけが残ります。 |
|
|
|
|
|